公園の木製ベンチにはおじさんが座っている。
おじさんは何をするでもなく、座っている。
街には小さな公園がいくつかある。川が街中を南北に突っ切り、東向きに流れを変えるところに小さな公園がある。川に面して川面に降りることができる石段があり、そこまで降りると、緩やかに曲がりながら本流まで辿り行く川水のたたずまいが感じられる。
「観光してんの?」
後ろから話しかけられた。
「観光してんの?」
振り向くと、小さな公園の木のベンチに座っていたおじさんである。
「いやいや、地元民ですよ。」
お互いしゃれた格好はしていない。
「なんだ、そう」
上に戻り、川に向かって右手方面にぶらぶらしていると、後ろからまたおじさんが
「それ知ってる?」と
公園の川に向かい右手奥、なかなか立派な幅2間ほどの横長の石碑を指さしながら近づいてくる。
「昔、はやったんだよなあ、」
「この辺じゃみんな歌ってたよ!」
「カラオケなんてないからさあ、今みたいじゃなく、ほらカセットテープでさあ。」
さかんに両手で小さな四角をつくりながら、懐かしがっている。
「そう、そう、昔はカセットテープですよねえ。」なんて極めて調子よく相づちを打つ。
「このあたりを歌った曲で、当時すごいはやっててさあ、とにかくみんな歌ってたよ。」
と、辺り一帯を腕で指し示しながら言う。
石碑には、昭和の流行歌手のヒット曲が刻まれている。
”大利根月夜” 作詞 藤田 まさと 作曲 長津 義司
「ああ、これ知ってますよお!」
「ヒットしましたよねえ。」
ヒットするも何も、”大利根月夜”は天保水滸伝の登場人物 ”平手 造酒”を歌ったもので、歌手”田端 義夫”さんのヒット歌謡である。天保水滸伝が千葉県東総地区を舞台とするので、この辺り一帯でとにかくよく歌われたことは想像に難くない。
「だよー、これはさあ、この辺じゃとにかくみんな歌ってたよ-」
「みんな歌ったんだよ!」それこそがヒットしたということだ!
「でもさ、土地の者でもこれあるの知らないヤツがいるよ。」
歌詞も終わりまでしっかりと刻まれているのだが、曲名とはじめの部分に、桜の細枝2~3本が石碑の右側からとびだしよく見えない。おじさんはその枝をひっつかみ
「これ邪魔でよく見えないけどさあ、」
持ち上げると曲のはじめの部分を歌い出した。
川の流れに溶け込みなかなかいい調子である。
確かに往年の大ヒット曲である。「ヒットしましたよねー」とまた極めて調子よく相づちをうつ。
鼻歌交じりになる。
川の畔には欄干がわたしてある。
欄干の縦の支柱に何本かの竹、1m程度の竹が麻縄で何本かくくりつけてある。
「おじさん、これなに?」
「ああ、それはさあ 7ヶ所参りって知ってる。」
「確か、正月の行事ですよねえ?」
「そう、お札をもらってくるやつ」
「あのお札を隣の町内との境目にこうやって括り付けとくんだよ。」
「ほら、お札の字がみえねえかな、」と重なった竹を動かそうとするが、思いのほかしっかりと麻紐で括られて、動く気配はない。
「町内によっては、自分とこの真ん中に祀っとくところもあるよ。」
知らなかった。
彷徨い、惑って、おじさんと邂逅し、この街の新しい事柄を知る。
これは、僥倖などではなく常にこの街の日常なのだ。
funaも歩けば公園のおじさんに当たる。佳き日!
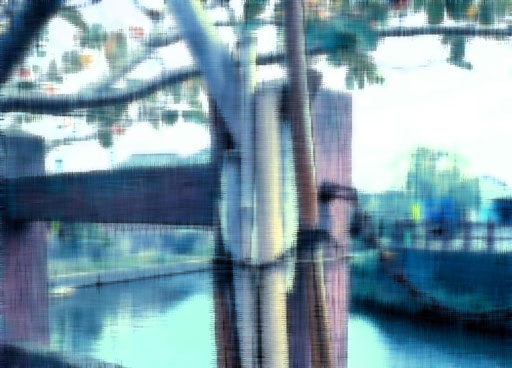
funa







コメント